相手の話がなかなか頭に入らないことってありますよね。
そういうときに「自分はダメなやつだ」と落ち込んでしまうかもしれません。
もしかして病気なんじゃないかとか、色々不安になることもあるでしょう。
しかし話が理解できないというのは、ちょっと聞き方を変えるだけで改善できるんですね。
これから訓練せずに話を理解する方法をお伝えしていきます。
人の話が理解できないならやるべきこと
理解力を高める話の聞き方
相手の話を理解するには、「誰」と「何」を意識して聞けばいいんですね。
多くの場合、人の話が理解できないのは、話の構造が理解できていないことによって発生しているんですね。
例えば、この文章は「誰」が「何」をしたでしょうか。
Aさんはお昼に出かけました
もちろん、「Aさん」が「お昼に出かけた」ということですよね。
実際の会話では色々な情報が付け足されてしまって、「誰」と「何」が分からなくなってしまうわけです。
実際の会話だと、これくらい情報が多いですよね。
Aさんは会議が長引いてしまったので、さっきBさんと一緒にお昼に出かけました
これも結局、「Aさんはお昼に出かけた」という話なんですよ。
だけど「会議が長引いた」や「Bさん」という情報によって、話が理解できなくなってしまうんですね。
だから話の理解力を高めるには、「誰」と「何」という2つのポイントを明確にして話を聞くことが大切です。
本当に「話を理解している」とできること
この「誰」と「何」を明確にすることによって、その話の中で足りない情報に気付くこともできるようになります。
例えば、こんな電話がきたらどう対応すればいいでしょうか。
A社の山下と申します。B社の高橋さんからの紹介で連絡させて頂きましたが、佐藤さんいらっしゃいますか?
この話の「誰」と「何」を整理すると、「山下さんは佐藤さんと連絡を取りたい」ということになりますよね。
まあ文字にすると簡単に見えますが、口頭で言われると混乱しちゃいますよね。「B社の高橋さん」って誰なんだろうみたいな。
そういう余計な情報を排除すると、「山下さんは佐藤さんと連絡を取りたい」ということになるわけです。
しかし、これだけでは佐藤さんと話をすることができません。ある情報が足りていないからです。
それは「どの佐藤さんなのか」という点です。
会社の規模にもよりますけど、佐藤さんだけじゃ分からないですよね。
部署やフルネームを確認しないといけませんし、なぜ佐藤さんと連絡を取りたいのかという用件も聞いておく必要もあるでしょう。
内容によっては佐藤さんが対応しない方がいい場合もありますよね。
このように「誰」と「何」を整理することによって、その話の中で必要な情報に気付くことができるようになります。
これは表面的に話を聞くだけではできないことですから、これができると本当に「話を理解している」と言えるでしょう。
それでも話が理解できないとき
ここまで話の構造が理解できれば、人の話は理解できるという話をしてきました。
しかし、話の構造が理解できても話の内容が分からない場合もあります。
それは純粋に知識が足りていない場合です。
専門用語など、話の中で使われている言葉の意味が分からないなら、理解できないのは当たり前ですよね。
そういうときは素直に勉強しましょうという話になるのですが、それでも話の構造を明確にすることは役に立ちます。
一例として、専門用語が出てくる文章を外務省から引用してみました。
持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
一文にこれだけの情報を詰め込めるのかっていう感じですけど、話の構造は何でしょうか。
構造としては「持続可能な開発目標とは、よりよい世界を目指す国際目標」ですよね。
そもそも「持続可能な開発目標」が分からねーよって感じかもしれませんが、「よりよい世界を目指す国際目標」であることは分かりますよね。
それでも話の内容がピンと来ないということは、知識の問題であることに気付けるわけです。
じゃあ知識を身につけようっていうことで、用語を調べればいいんですね。
つまり話が理解できないというのは、「分からないところが分からない」という状態なんですね。
だから話の構造を明確にして、何が分からないのかをハッキリさせればいいわけです。
分からないところがハッキリしたら、後はそこを学べばいいということです。
まあ実際の会話の中で知らない専門用語がバンバン出てくると、混乱してしまうと思います。
だけど「今どの話をしているのか」という意識を持ちつつ聞くことは大切です。
そうすれば話の全体像は理解することができるようになります。
まとめ
今回は、人の話が理解できない方に対して、理解力を高める方法について話をしました。ちょっとした聞き方、意識の向け方の違いなんですね。
話の構造を整理すれば、話の理解力を高めることはできます。
それと同時に「何が理解できないのか」も明確にできるようになります。
この「何が理解できないのか」が分かるのは、意外と重要なことではないでしょうか。
なぜなら分からない部分が明確になっているので、「この部分をもう少し詳しく教えていただけますか」とお願いすることができるからです。
状況にもよりますが、一度で理解できないなら、二度目で理解すればいいんですね。
ただ同じ話をもう一度させるわけにはいかないので、何が理解できて、何が理解できなかったのか。この点を明確にして、話を聞いておくことが重要です。
だから是非「誰」と「何」を意識して話を聞いてみてください。



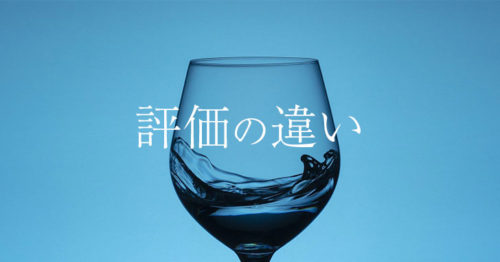


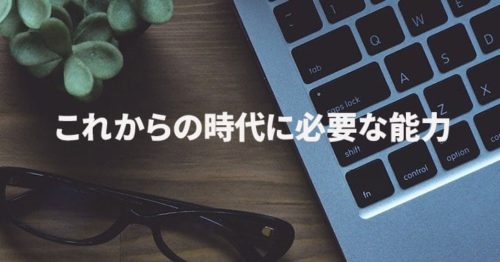
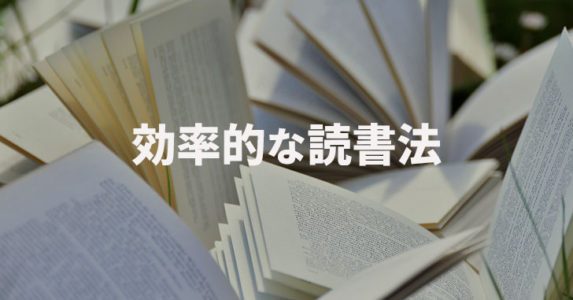







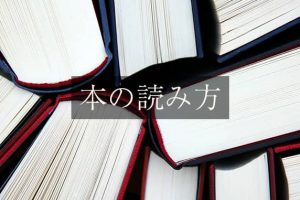

コメントを残す